相手に合わせる力~共感と適応のコミュニケーション
こんにちは!このブログも第6回となりました。今回は「相手に合わせる力」に注目します。
人間関係がスムーズになるかどうかは、「自分の話し方」だけでなく、「相手に合わせる柔軟さ」も大きなポイントになります。
私たちは、年齢、性格、価値観、経験などが異なる人と毎日コミュニケーションをとっています。
だからこそ、「この人にはどう伝えたら伝わるか?」と考えることが、より良い関係を築く第一歩になります。
■ 相手に合わせる=相手を尊重すること
「相手に合わせる」というと、なんだか我慢することのように思う人もいるかもしれません。
でも、本質は「相手をよく見て、受け止めようとする姿勢」にあります。
たとえば:
- 子どもには、ゆっくり・わかりやすく説明する
- 上司には、結論を先に簡潔に伝える
- 高齢者には、敬意と丁寧さを意識する
相手が受け取りやすい言い方・態度を選ぶことは、相手を大切にする行動です。
■ 事例:話し方を変えて関係が好転したIさん
Iさん(40代・福祉施設職員)は、新人スタッフJさんとの会話に悩んでいました。
Iさんはベテランで、説明もスピーディ。しかしJさんは要領をつかむのが苦手で、何度も質問してきます。
最初は「なんでこんなこともわからないの?」と感じていたIさんでしたが、「Jさんのペースに合わせてみよう」と決め、説明のしかたを変えてみました。ゆっくり話し、図やチェックリストを使うようにしたところ、Jさんの理解が深まり、ミスも減っていったそうです。
■ タイプ別コミュニケーションのコツ
| 相手のタイプ | コミュニケーションの工夫 |
|---|---|
| 話し好きな人 | 話をよく聞き、適度に相づちを打つ |
| 無口な人 | 焦らず、短い言葉で安心感を与える |
| 論理的な人 | 理由やデータを添えて話す |
| 感情的な人 | 気持ちに共感しながら伝える |
人はそれぞれ「受け取りやすいスタイル」があります。それに寄り添うことで、対話のストレスがぐっと減ります。
■ 職場・家庭で活かせる「合わせる力」
【職場の例】
- チームリーダーが、メンバーの性格に応じて指示の出し方を工夫する
- 会議では、口数の少ない人にも話しやすい雰囲気をつくる
【家庭の例】
- 思春期の子どもには、詰問せずに「どう思ったの?」と投げかける
- 高齢の親には、昔話にもじっくり耳を傾ける
「わかってもらおう」より「わかろうとする」。この姿勢が信頼を生み出します。
■ おわりに
「合わせる」というのは、自分をなくすことではありません。
相手の立場や気持ちに目を向けることで、かえって自分の言いたいことも伝わりやすくなるのです。
次回は、「対立を乗り越えるコミュニケーション」をテーマに、意見の違いやぶつかり合いをどう前向きに乗り越えるかを考えていきます。どうぞお楽しみに!

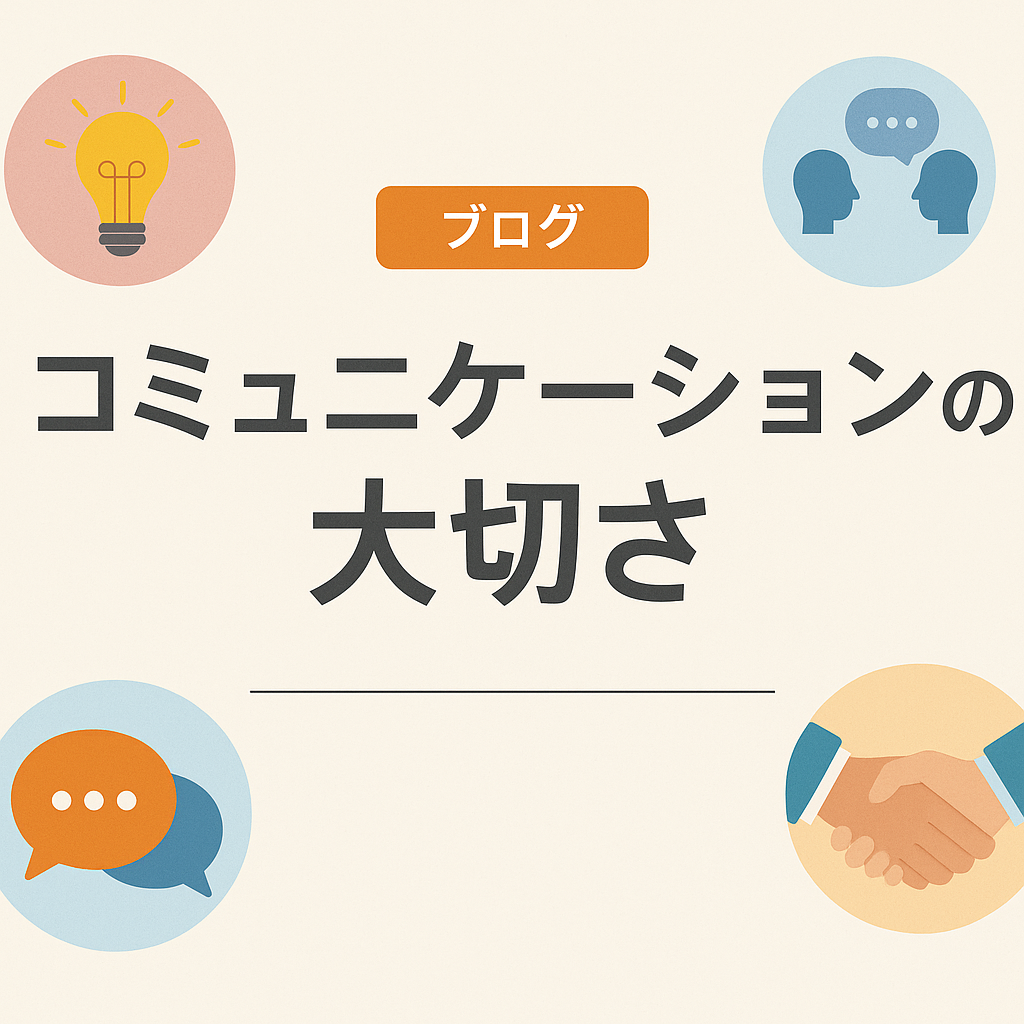
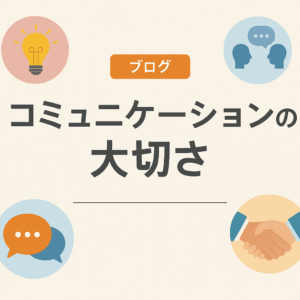

コメント